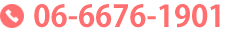マニュアル作成に必要な5つの観点
投稿日:2025年04月23日
カテゴリー:レビュー
投稿者:
J(ジェイ)

マニュアルを作成したいと思ったとき、まずどんなことを考える必要があるでしょうか。
今回は、企画時におろそかに(あるいはおざなりに)されがちな観点を5つ紹介したいと思います。
1. 対象の製品やサービスは何か
2. 誰がその製品やサービスを使うのか
3. 誰がその製品やサービスのマニュアルを読むのか
4. どのような場面でマニュアルは読まれるのか
5. マニュアルの媒体は何が適切か(紙、Web、アプリ組み込み、動画など)
1は考えるまでもないと思われるかもしれませんが、説明する対象(製品・サービス)をよく理解し、伝えるべきことを把握することが、マニュアル作成に向けての第一歩とも言えます。
当社の場合、テクニカルコミュニケーターは、実際の製品をお借りしたり、開発資料などを確認させてもらったりすることで、対象の製品やサービスをしっかり理解することから始めます。
全く新しい製品の場合だと、たくさんある機能のなかで、
開発者自身も「何をどこまで説明すればよいのか」を把握しきれていないことがあります。
そんなときは、製品のコンセプトや使用場面のイメージをヒアリングしながら、必要な情報を一緒に洗い出すことも行います。
開発段階では、全部の機能が実際に確認できないこともあるため、様々な資料を頼りに制作が進んでいきます。
マニュアル作成においてまず考えるべきこととして「製品・サービスの理解」を挙げましたが、これは最初だけでなく、完成した製品を目の前に置いて、マニュアルの内容が正しいのか、説明しそびれている項目がないかをチェックする最終工程に至るまで、継続して考える必要があるポイントです。
次に、2の「誰が製品やサービスを使うか」も、マニュアルの内容を考えるうえで重要です。
簡単な例でいうと、一般のユーザーが使う家電製品なのか、工作機械のように専門知識を持った技術者が使う製品なのかで、どれだけかみ砕いた説明にするべきかの基準が変わってきます。
専門家に向けたマニュアルの場合、基本的な知識はあらかじめ持っているという前提で、すべてを書き下す必要はないかもしれませんし、専門用語も一言一句説明する必要はないかもしれません。
ただし、これは、3の「誰がマニュアルを読むのか」によっては、少し調整が必要です。
例えば、技術者に向けた施工マニュアルであった場合でも、何らかの事情で施工不良が多く発生していたり、人材不足が影響して読み手の知識の差が問題になっていたりする場合は、読み手の熟練度によって必要な情報に到達できるような工夫が必要かもしれません。
また、介護用品などのように、製品を使う人と製品のマニュアルを読む人が明確に違う場合もあります。
この場合、4の「どのような場面で読まれるか」を考えながら3の「誰がマニュアルを読むのか」を考える必要があります。
例に挙げた介護用品の場合、機器の全体を通した機能の把握やメンテナンスについては、ご家族が読み手となるかもしれませんが、使用頻度が高い機能に関する簡単ガイドのようなものであれば、機器を使用する人(例えば高齢者)自身が読む場合もあるかもしれません。
後者の需要が高いと想定される場合、簡単ガイドは大き目の文字で、識別しやすい色使いが必要になりますし、一方でマニュアル本体についてはそこまで大きな文字である必要はなさそうです。
最後に、5の「マニュアルの媒体を何にするか」も必ず考察すべき項目です。
「紙のマニュアルは今後減っていくだろう」と予想されるようになってからずいぶんと経ちますが、近年のAIの目覚ましい進歩により、これまで以上に紙以外の媒体が活用されるようになることが考えられます。
Webや動画、そしてAIを活用したChatbotなど、これまでのマニュアルの常識を覆すようなマニュアルがスタンダードになるかもしれません。しかし、重要なのは、先にみてきた4つのポイントをしっかり考慮したうえで、それぞれのケースに最適な媒体を選んでいくことです。
マニュアル作成にあたって、実際にはもっと細かく、情報の構造化、文字サイズ、デザイン、レイアウト、さらには制作効率など、様々なことを考慮しながらどんなマニュアルにするかを決める必要があります。
しかし、今回挙げた5つの観点抜きにして適切に決めることは非常に困難です。
今回は、マニュアル作成のマニュアルがあるとしたら必ず挙げられる5つの項目について、お話をさせていただきました。